[005] 「音読」はしなくていいのか?
パブリック・コメント|音読|適切さ|正確さ|評価の観点
こんにちは、anfieldroadです。
4号まで出してみて、なんとなく週2回くらいのペースでNewsletterを発行していけそうな見通しが立ってきました。読者のみなさまも日々お忙しいでしょうから、それくらいのペースでないと読む暇がないですよね。1回の量もほどほどにしながら、読みやすいものになるように、工夫をしていきたいです。
パブリック・コメントから考える②
新しい学習指導要領に関しての疑問点を整理するために、2017年に私が提出したパブリック・コメントをご紹介しております。前回の「目標」に続く2つめは、「音読」についてです。
すでにお気づきの方もいらっしゃるかも知れませんが、このコメントにはお恥ずかしながら事実誤認があります。実は、現行も新も学習指導要領には「音読」について記載があります。ですので、「まったく触れられていない」というのは事実誤認です。申し訳ありません。
学習指導要領 対照比較表(文部科学省)
まぁ、それぞれここ1箇所だけなんですけど。
そして言い訳になりますが、当時私がそのように思い込んで書いてしまった背景には、国立教育政策研究所が当時出していた「評価規準の作成のための参考資料」に、「音読」という文字が1回も出てこない、という事実に憤っていたということがあるのだと思います。
音読は「適切さ」だけでいいのか?
さて、それでも学習指導要領における音読の扱いに対して疑義を唱えておくと、音読はあくまで「適切さ」の文脈で指導しようと促しているのはいかがなものか、ということです。
現行においては「音読する」の前に「その内容が表現されるように」という枕詞がついています。現行の「外国語表現の能力」「外国語理解の能力」という評価規準では、「正確さ」と「適切さ」という2つのカテゴリがありますが、これはまさに「適切さ」に該当する指導内容だと言えます。
そして、新指導要領ではこの項自体が〔思考力,判断力,表現力等〕という枠組みの中に位置しています。このへんについては後ほどもっと詳しく扱いますが、新指導要領では〔知識,技能〕ではいわゆる「正確さ」を、〔思考力,判断力,表現力等〕では「適切さ」を指導・評価するように設計されている節があります。
となると、学習指導要領においては「正確な音読」を指導することはいっさい想定されていないということになります。そこまで考えたうえで上記の私のパブリック・コメントをお読みいただけると、多少はそこで提起している問題の大きさを理解していただけるのではないかと思います。
「正確さ」だけが大事ではないと思いますし、「適切さ」がしっかり指導・評価されるようになっていくことは望ましいと思います。それでも、コミュニケーションを円滑に進めるためには、最低限必要な正確さは存在すると思いますし、「適切さ」はその「正確さ」の上に成り立つもののはずです。
文科省には実際の中学校の教室でどんな学習活動がおこなわれているのかを(実施状況調査のようなアンケート等だけでなく)しっかりと把握する努力をしてもらいたい、と思っています。
前回ご案内したところ早速イイね!の♡をたくさんいただきました。どうもありがとうございます。
その横の吹き出しマークからはブログ等のようにコメントを書くこともできます。ご質問やご意見などもお寄せいただけると励みになりますし、次回以降の貴重な話題にもなりますので、大変ありがたいです。



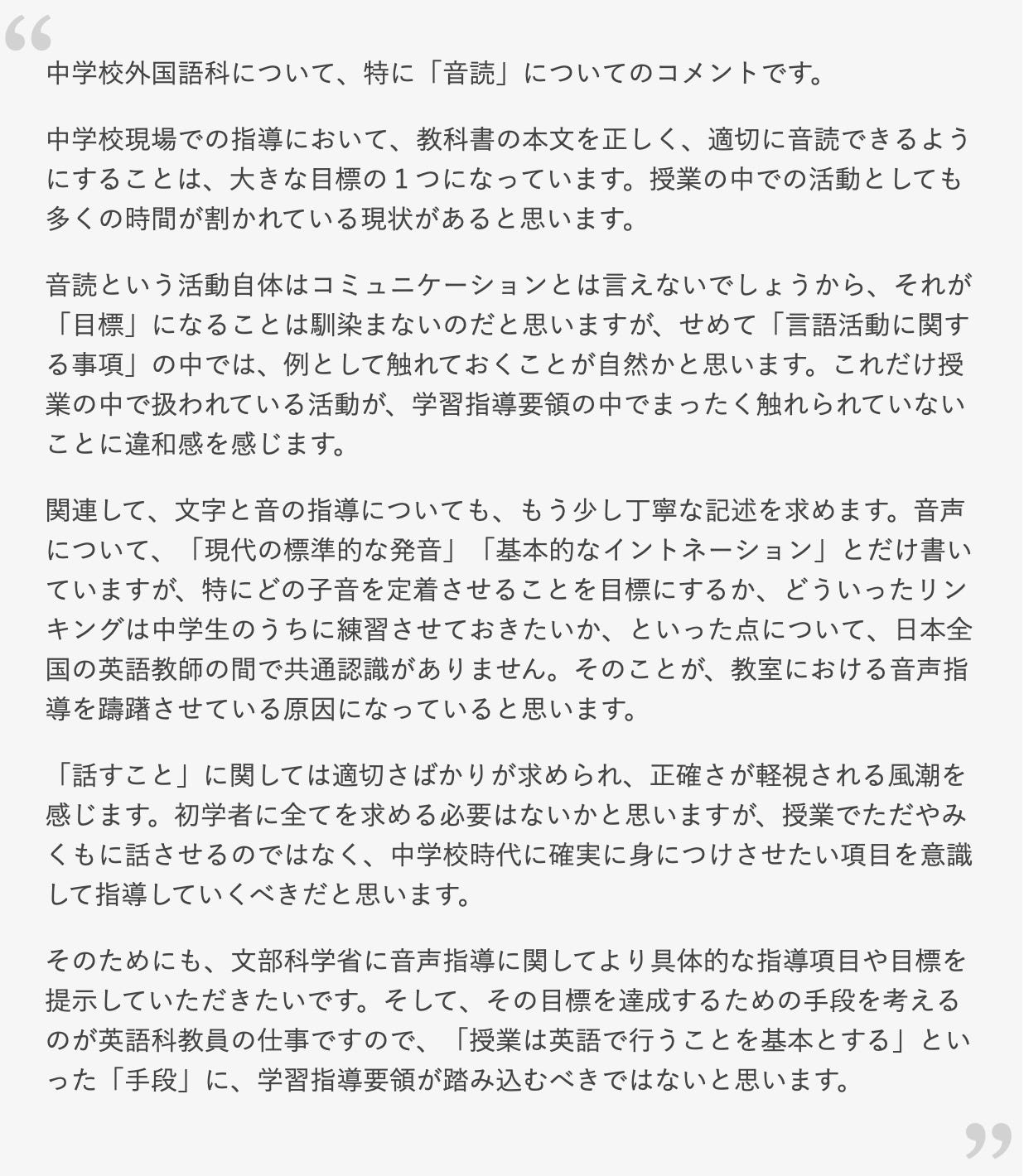

コメントありがとうございます。はい、私も発刊後に改めて読んでみて、その辺の記載を見つけました。次号でフォローしようと思います。
アリバイ的に書かれてる感もありますし、音読は「話すこと」ではなくあくまで「読むこと」に位置づけられていることも、興味深いので、次号でその辺を書かせていただきます。
毎回楽しく読ませていただいております。
音読の「正確さ」について、私も気になって新指導要領の[解説]を読んでみたのですが、一応p.58に記してあるように思います。
>一方,音読は,黙読とは異なり,声に出して読むことであり,書かれた内容が
表現されるように音読するためには,説明文,意見文,感想文,対話文,物語な
どの意味内容を正しく理解し,その意味内容にふさわしく音声化する必要がある。
声に出して読む必然性のある活動として,読み聞かせやアナウンス,ニュース
などが考えられる。発音・アクセントの正確さとともに,間の取り方等を考えな
がら,相手に伝えるために読むという活動は効果的である。(引用終わり)
ただ、思考力,判断力,表現力等の項目ですし、anf先生のおっしゃるようにこの領域は「適切さ」を重視するところなので、そこにシレッと「正確さとともに」なんて書かれても...とも思います。
音読はスピーキングへの橋渡しとして重視したい活動なので、今後も頑張っていきたいと思っています。
読んでいただきありがとうございました。