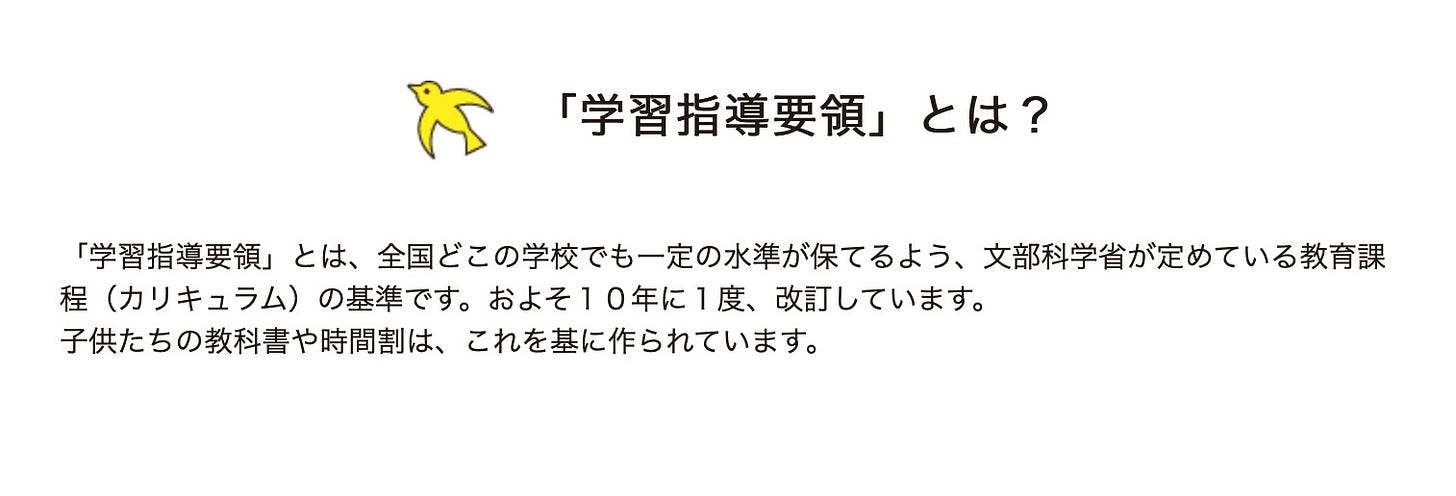こんにちは、anfieldroadです。
Newsletterにご登録いただいたみなさん、どうもありがとうございます。最初のうちは何も届かいないと面白くないでしょうし、私もSubstackの仕組みをまだ十分に把握できてないのでいろいろ試したいし、冬休みだし、ということでしばらくは配信頻度がやや高めかも知れません。一回分の量が長くなり過ぎないように気をつけながら、ちょくちょくお送りさせていただくと思います。
Why 学習指導要領?
さて、このNewsletterで取り上げるのは学習指導要領です。
Newsletter始めるのに、あえてこのお堅いテーマを選んだ理由は、前号でも書いたように、あと3ヶ月でスタートするというのにまだあんまりよくわからない、という先生方も多いと感じているからです。本来であれば来年度に向けて、2020年は準備の1年になるはずだったのでしょうが、コロナ禍によりそれどころじゃなくなってしまいましたね。
それでも今回の改訂をよく理解しないままスタートしてしまうのが危険だと思うのは、今回は評価の観点が変わるからです。学習指導要領がどう変わろうと、教科書がどう変わろうと授業は変えないぞ、みたいな強気な人でも、評価の観点が変わるとなるとさすがに意識せざるを得なくなるのではないかと思います。
What’s 学習指導要領?
さて、そもそもなお話になりますが、学習指導要領というのは、どういう位置づけにあるものでしょうか。文科省のサイトでは、以下のように紹介されています。
[ 学習指導要領の基本的なこと(文部科学省)]
私はよく学生に「10年に1回変わっちゃうものを一生懸命暗記するより、その先40年くらい使うことになる自分の頭を鍛えなさい」という話をします。また、今回の改訂内容は個人的に納得できないところがあって(パブリックコメントも提出しました!)、ブログ等でも結構辛口に書いてきました。
それでも、「全国どこの学校でも一定の水準が保てるよう」というこの文書の存在理由は理解できるし、教師にどんなことが期待されているのかくらいは知っておくべきだろうとは思っています。だから、この機会にちゃんと読んでおこうと思うのです。
How‘s 学習指導要領?
でも、学習指導要領って読みにくいですよね。私も学生に教えるとなって結構一生懸命読み込んだのですが、今回のやつは今まで以上に読みにくい。「解説」も含めてこれらの「経典」がわかりにくいことをいいことに、「解釈」を「伝達講習」することで教員をコントロールしようとしているんじゃないか、と勘ぐりたくなるレベルです。
だから、「文部科学省や教育委員会がこう言ってた」みたいにお上の解釈を有難がるんじゃなくて、それぞれの先生方が学習指導要領を読んだ上で「俺はこう思う」とか「私はこうしたい」って言えることが大事ですよね。(とはいえ学習指導要領のほうにそんな多様な先生方を受け容れる度量があるのか、というところも疑問ですけど。)
ということで、このNewsletterでは、学習指導要領をクリティカルに読み解いていきたいと思います。次号では(総論はもう耳タコかも知れませんが)新学習指導要領改訂のポイントを確認します。これ書くために私もまた(読みにくい)学習指導要領を読み直しているので、なんだか私の勉強になっている気もします。
これまでに発行されたNewsletterはまだ2号だけですけど、登録前までに配信されたメールはアーカイブというページで読めますので、よかったらそちらも御覧ください。